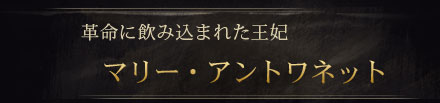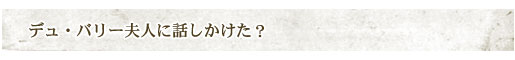| Ⅰ. | ヴェルサイユ宮殿 |
| Ⅱ. | マリー・アントワネットに 対する中傷 |
| Ⅲ. | 首飾り事件 |
| IV. | フランス革命 |
| V. | 囚われの身 |
| VI. | タンプル塔 |
| VII. | コンシェルジュリー |
| VIII. | 王妃の裁判 |
| IX. | マリー・アントワネット 最期の日 |
| 母. | マリア・テレジア |
| 夫. | ルイ16世 |
| 息子. | ルイ17世 |
| 長女. | マリー・テレーズ |
| 義妹. | エリザベート |
デュ・バリー夫人、本名マリ=ジャンヌ・ベキュー。アンヌ・ベキューの私生児として、フランスのシャンパーニュ地方の貧しい家庭に1743年8月19日に誕生しました。ソフィア・コッポラ監督の映画『マリー・アントワネット』では、下品な意地悪女という表現と演出がされていますが、実際はシルバーブロンドの美しい髪に、決め細やかな白い肌をした美しい女性でした。


最下層の生まれにも関わらず、ジャンヌはルイ15世の公妾まで登りつめます。お針子をしていましたが、体を売る商売で生計を立てていました。
20歳のときに、『パリ一の極悪人』と悪名高いデュ・バリー子爵がジャンヌの美貌に目をつけて、一緒に住むようになります。そして、子爵が連れてくる男たちとベッドを共にするようになります。客は、大貴族やアカデミー会員といった大物ばかりだったので、自然とジャンヌは宮廷でも通用するような作法や会話術を身につけていきました。

デュ・バリー子爵は、25歳になったジャンヌをヴェルサイユ宮殿に連れ出しました。公妾のポンパドール夫人をなくして、癒しを求めていた58歳のルイ15世は魅力溢れる若いジャンヌに虜になりました。子爵はジャンヌの立場を強くするために、自分の弟と結婚させて、ジャンヌの名前はデュ・バリー伯爵夫人としたのです。
ジャンヌの夫となった弟は、結婚から数日後に謎の死を遂げています。こうして、デュ・バリー夫人となったジャンヌは、ポンパドール夫人の後釜として、ルイ15世の公妾になったのです。ブルジョワ階級で教養も知性もあったポンパドール夫人でさえ宮廷内の反発は大きかったのに、デュ・バリー夫人は政治経済に無関心で、ルイ15世をできる限り仕事から遠ざけるように仕向けていました。ポンパドール夫人が政治に関わっていたのに対し、デュ・バリー夫人は贅沢に暮らすことだけが望みだったのです。
 オーストリアから王太子妃としてヴェルサイユに嫁できたマリー・アントワネットにとって、公妾がいることも驚きでしたが、その人物が、自分の大嫌いな娼婦出身だということにかなりのショックを覚えます。
オーストリアから王太子妃としてヴェルサイユに嫁できたマリー・アントワネットにとって、公妾がいることも驚きでしたが、その人物が、自分の大嫌いな娼婦出身だということにかなりのショックを覚えます。
宮廷内では先に低位の者が高位の者に声をかけることは許されません。アントワネットは当然のようにデュ・バリー夫人を無視します。それはもう、徹底的に無視をしたのです。ヴェルサイユのしきたりを利用して、デュ・バリー夫人に、侮辱と恥をかかせたのです。
宮廷内は、いつアントワネットが話しかけるのか、大いに盛り上がりました。デュ・バリーがルイ15世に告げ口をして泣きつき、怒ったルイ15世はオーストリア大使に圧力をかけ、オーストリアの女性、アントワネットの母が『声くらいかけてあげなさい』という手紙をアントワネットに送ることにまで発展してしまいました。
実家の母にまで説得をされ、しかたなくいつ、どういう形でデュ・バリーに話しかけるかの段取りが決められるのですが、話しかけようとすると、叔母たちが邪魔をしたり(デュ・バリー夫人を嫌っていた)、アントワネットがあっさりと負けるのを嫌がって約束を破ったりと、中々実現しませんでした。
1772年元旦。宮廷で開かれていた大祝賀会でのこと。宮廷婦人らが挨拶をしにアントワネットに歩み寄ってきます。その中に、デュ・バリー夫人が大臣の妻、エギヨン伯爵夫人と並んでいたのです。アントワネットはエギヨン伯爵夫人には自然な態度で言葉をかけましたが、デュ・バリー夫人には、微妙な角度で頭を巡らせ、独り言のように『今日のヴェルサイユは大変な賑わいですこと』と言ったのです。こうしてアントワネットとデュ・バリー夫人との対立に、ひとまず決着がついたのです。
 公妾は、国王がなくなったら宮廷から去らなければいけません。それは最初から分かっていることなので、いざというときのために、しっかりと財蓄しておくのです。
公妾は、国王がなくなったら宮廷から去らなければいけません。それは最初から分かっていることなので、いざというときのために、しっかりと財蓄しておくのです。
デュ・バリー夫人は、現金や宝石はもちろんのこと、名画である『チャールズ1世像』まで所有していました。デュ・バリー夫人はルイ15世なきあと、パリ郊外の邸宅で、何人もの愛人を相手に悠々自適の暮らしをしていました。飲んで笑って食べて……こうした暮らしをしていくうちに、素晴らしいプロポーションもどこにいったのか、体はすっかり弛緩し、面影がないほど肥満していました。
こんな王侯貴族相手の自堕落で無駄にお金持ちの女は革命派の敵です。愛人のド・ブリサック元師が革命派によって命を奪われたとき、デュ・バリー夫人はありったけの財産を持ってイギリスに逃亡しました。そのまま亡命生活を続けていればよかったのですが、どういうわけか彼女はパリに戻ってきます。
残してきた宝石を取り返しにきたという説もありますが、もしそれが本当であれば、大変おろかな行動です。もちろんすぐに逮捕され、断頭台に送られます。執行人のサンソンは昔の恋人だったらしく、泣いて命乞いをします。命が惜しくて断頭台のまわりを動物のように吠えながら逃げ回り、見物に集まった民衆に命乞いをしたと言われています。本当の貴族ではないため、貴族としてのプライドがないのでできることです。
サンソンは自分で刑を執行できず、息子に刑の執行をさせました。愚かに逃げまわり、みっともなく叫んだデュ・バリー夫人ですが、これまで断頭台の犠牲になった貴族たちが、デュ・バリー夫人のように泣き叫んでいたら、もっと早く恐怖政治は終わっていたと言われています。皆貴族の誇りを持っていたので、取り乱すことなく、凛として刑を受けたのです。